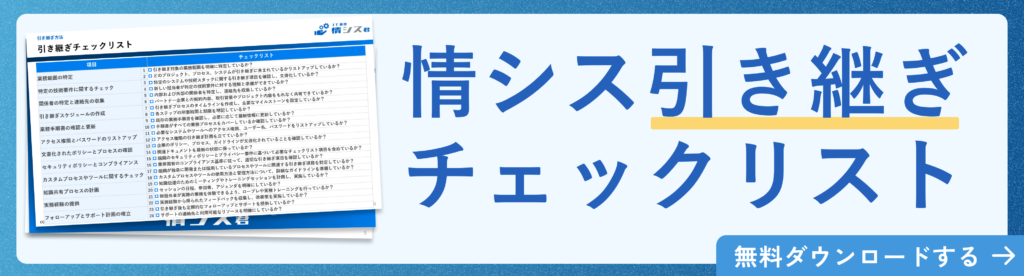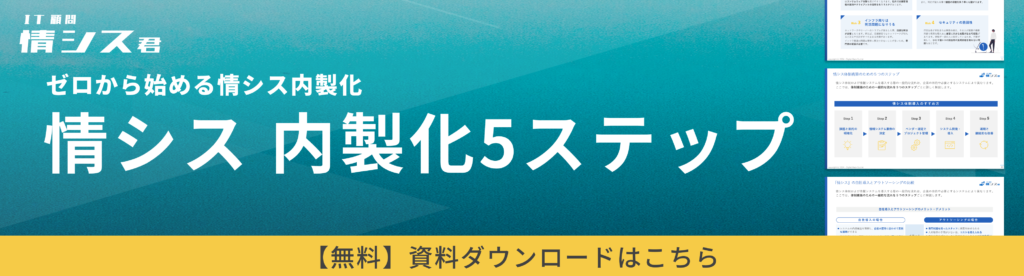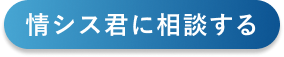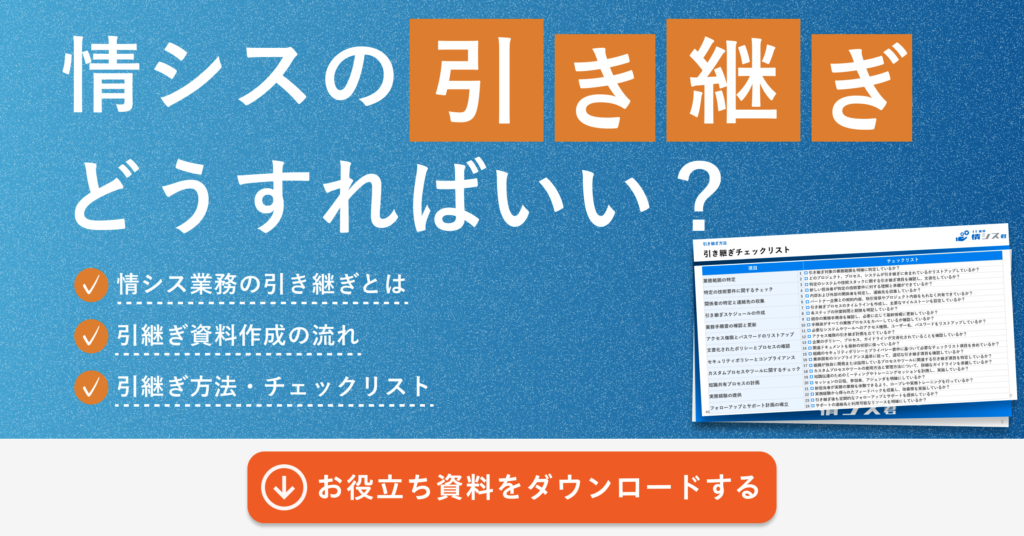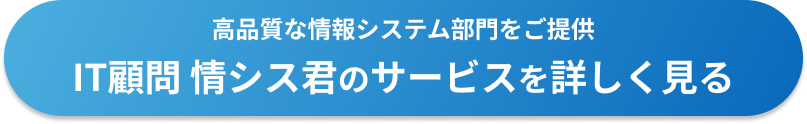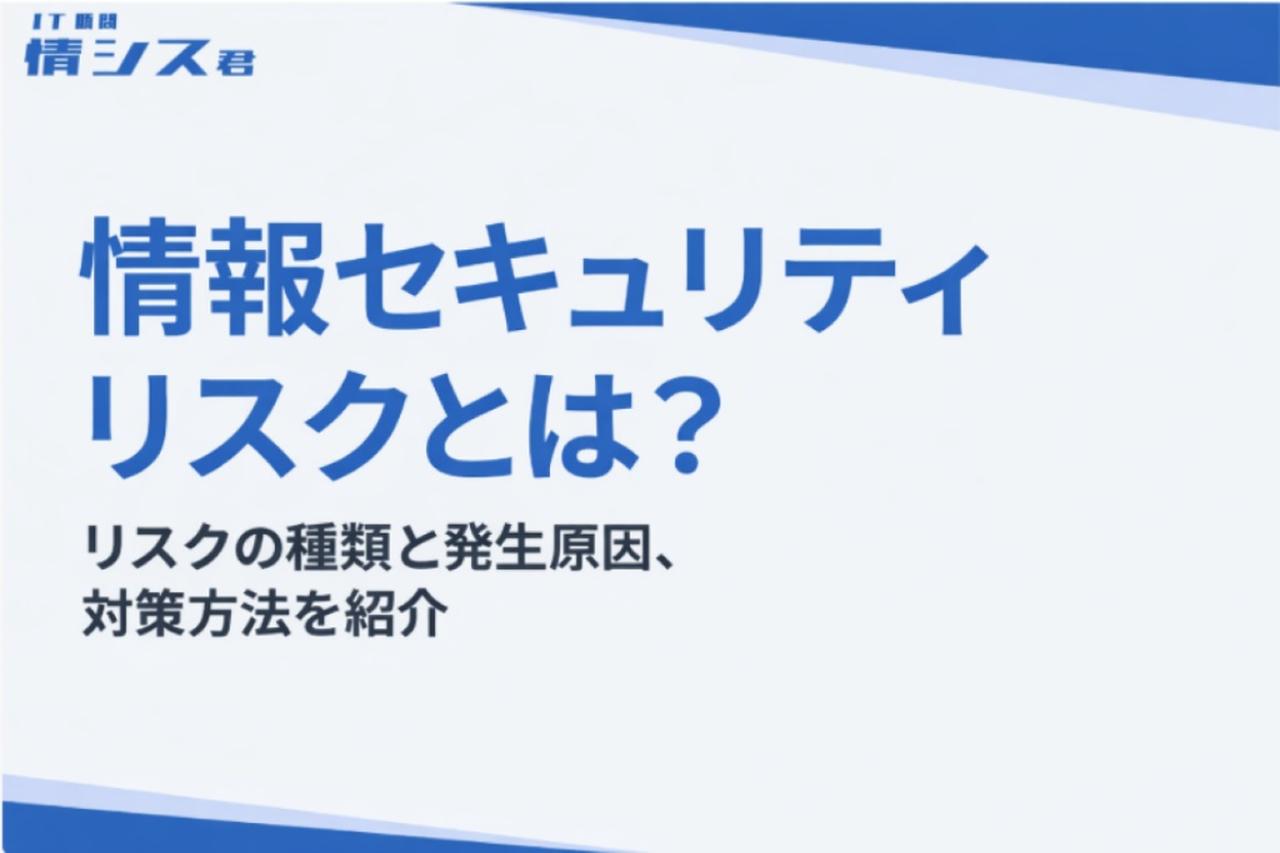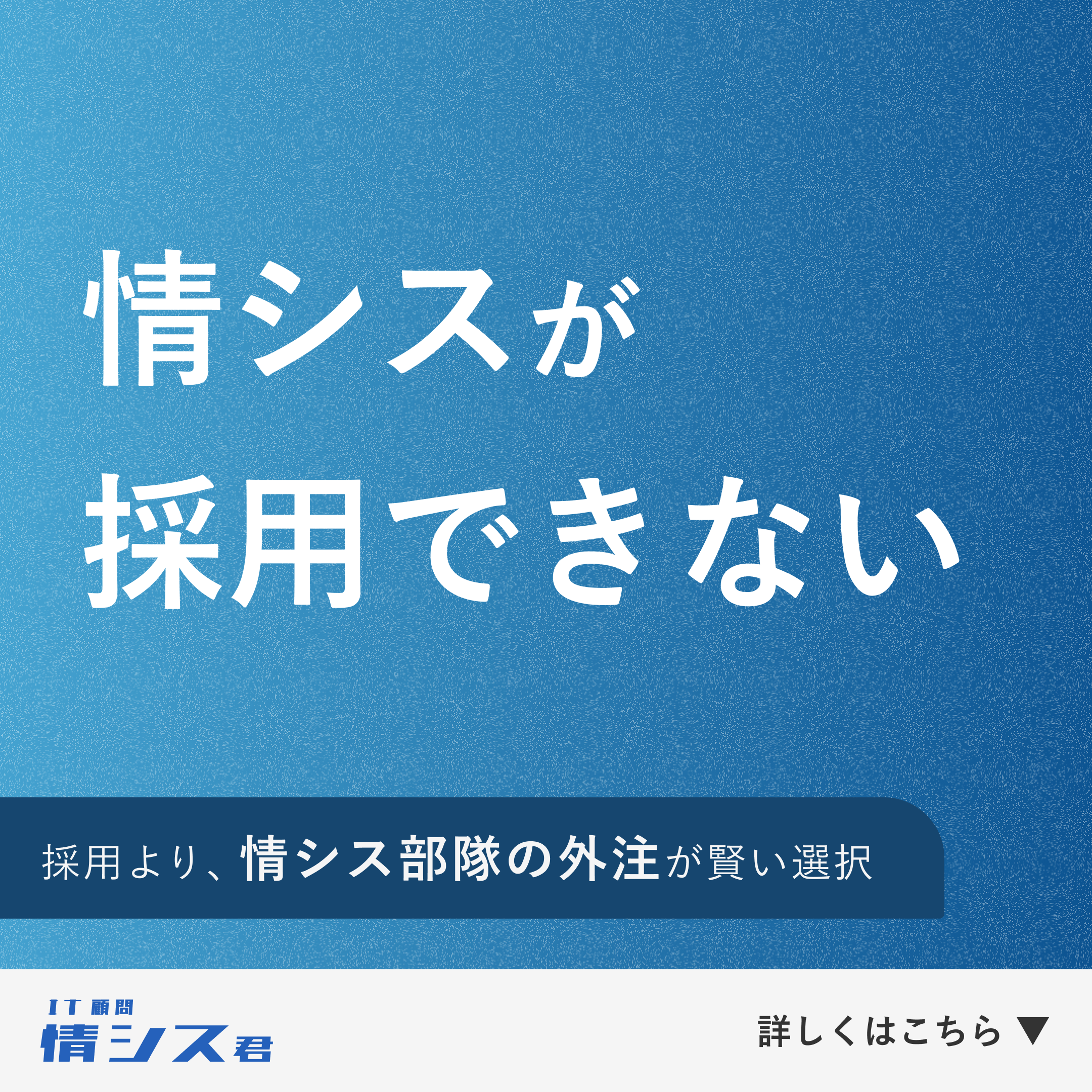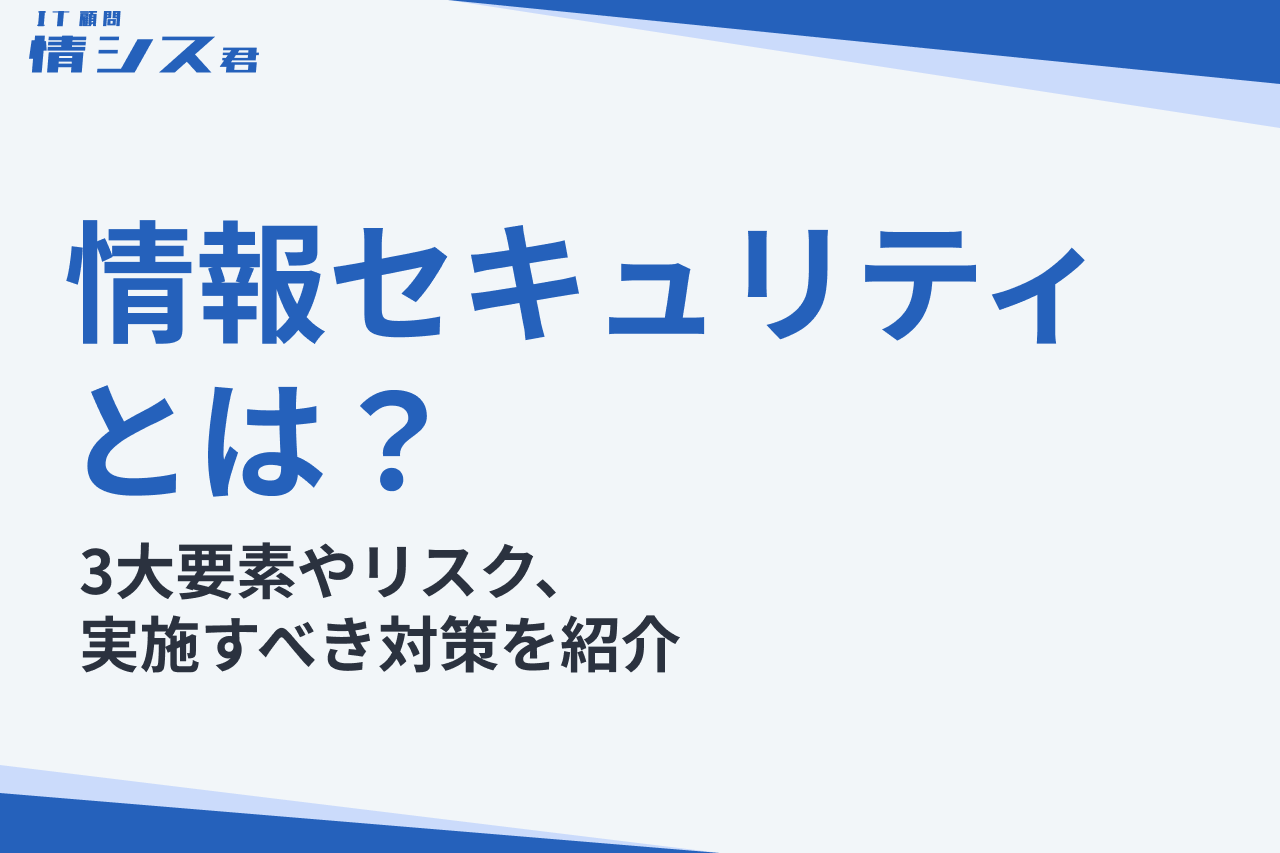
近年、企業の情報資産を狙ったサイバー攻撃や情報漏えい事件が増加しています。適切な対策を講じなければ、機密情報の流出や業務の停止といった深刻な被害につながる可能性があります。
「情報セキュリティという言葉は聞いたことがあるけれど、内容がよくわからない」
「具体的にどのような対策が必要かわからない」
このような疑問・悩みを抱えている方に向けて、本記事では、情報セキュリティの基本概念や3大要素(CIA)、情報セキュリティのリスクと対策などをわかりやすくまとめました。企業が実施すべき具体的な情報セキュリティ対策も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
\情シスの引き継ぎにお困りの方必見 !資料ダウンロードはこちらから/
目次
情報セキュリティとは?
情報セキュリティとは、企業の情報資産や、それを管理・保管するシステムを外部の脅威から保護する取り組みのことです。
IT化が進む現代では、情報漏えい・不正アクセス・データ改ざんなどのサイバー攻撃リスクが増加しており、企業は常にこれらの脅威に晒されています。さらに、雷や火災などの自然災害によるサーバー故障やデータ消失も、業務停止を招く重大なリスクの一つです。
こうしたリスクを最小限に抑え、安全な運用を維持するために、企業は包括的な情報セキュリティ対策を講じる必要があります。
情報セキュリティの強化は、単なるIT施策ではなく、企業の信頼を守り、事業継続性を確保するための重要な取り組みです。
情報セキュリティにおける情報資産とは
情報資産とは、企業が保有するデータや情報、それに関連する全ての資産を指します。代表的な情報資産として、以下のようなものが挙げられます。
| 種類 | 具体例 |
| 情報 | 顧客情報、機密資料、財務データなど(紙の資料も含む) |
| ソフトウェア | 業務システム、アプリケーションなど |
| ハードウェア | サーバー、PC、USBメモリ、ハードディスクなど |
| 通信インフラ | インターネット回線、VPN、Wi-Fiルーターなど |
| クラウドサービス | クラウドストレージ、SaaS、メールサービスなど |
これらの情報資産を適切に管理しないまま運用すると、漏えいや不正アクセスが起きた際に企業の信用を大きく損なうおそれがあります。そのため、企業はセキュリティ対策を講じて、情報資産が悪用されないように保護しなければなりません。
情報セキュリティの3大要素(CIA)

情報セキュリティを確保するための基本的な概念に、以下の「3大要素」があります。それぞれの頭文字をとって「CIA」とも呼ばれます。
- 機密性(Confidentiality)
- 完全性(Integrity)
- 可用性(Availability)
企業の情報資産を適切に管理するには、3つの要素をバランスよく高めることが重要です。それぞれの要素について詳しく解説します。
機密性(Confidentiality)
機密性とは、許可されたユーザーやシステムだけが情報を閲覧・使用できるように制御することです。
機密性が確保されていないと、情報流出による企業の信用失墜や法的責任につながる可能性があります。そのため、データの暗号化やアクセス制御を強化し、必要最小限のユーザーだけが情報にアクセスできるルールを整備することが不可欠です。
適切な対策を実施することで、機密情報の保護を強化し、企業のリスクを最小限に抑えることができます。
完全性(Integrity)
完全性とは、保有する情報が正確かつ最新であり、改ざんや破損がない状態を維持することを指します。たとえば、顧客データの更新が正しく処理され、古い情報が適切に管理・更新されている状態は、完全性が高いといえます。
完全性が損なわれると、誤った契約内容や不正確な数値に基づく判断により、金銭的損失や企業の信用低下につながります。そのため、データの正確性を維持するための対策を講じることが不可欠です。
適切な管理を実施することで、情報の正確性と信頼性を維持し、安全な業務運用を実現できます。
可用性(Availability)
可用性とは、必要なときに情報へアクセスできる状態を維持することを指します。可用性が低いと、従業員が必要な情報を取得できず、業務効率が大幅に低下するリスクがあります。そのため、システム障害や自然災害が発生しても、速やかに復旧できる体制を構築することが重要です。
可用性を高めるためには、サーバーやネットワーク機器の冗長化、定期的なメンテナンス、バックアップの保管などの対策が求められます。こうした対策を講じることで、企業の事業継続性を高め、安定した運用を維持できます。
情報セキュリティの追加要素「4つの新要素」とは?
最近では、従来の3大要素に加えて、より包括的なセキュリティ対策を実現するために、「4つの新要素」が重要視されるようになっています。
・真正性(Authenticity)
許可のない人や端末が不正にアクセスしないようにすること。IDとパスワードだけでなく、多要素認証を導入し、利用者が本人であると確認できる方法が求められます。
・信頼性(Reliability)
システムやデータが意図したとおりに動作・処理され、結果が正確であるよう担保すること。これには開発時のテスト体制や運用ルールを強化し、ヒューマンエラーを減らすことが大切です。
・責任追跡性(Accountability)
誰が、いつ、どのような操作を行ったか後からでも確認できるように履歴を残すこと。ログを詳細に取得することで、ログを追跡し、原因を特定できます。
・否認防止(Non-Repudiation)
トラブルやインシデント時に、責任者が「自分はやっていない」と言えないよう証拠を確保すること。ログや署名付き記録を厳重に管理し、証拠を信頼できる形で保持することが重要です。
CIAの3要素に加えて上記の4要素も加えることで、より強固なセキュリティ対策が期待できます。
情報セキュリティにおけるリスクの種類
適切な情報セキュリティ対策を講じるためには、リスクの種類を理解することが大切です。情報セキュリティにおけるリスクの種類は、「脅威」と「脆弱性」に分類できます。
なお、情報セキュリティリスクについては以下の記事でも詳しく解説しているので、くわしく知りたい方はこちらをご覧ください。
関連記事:情報セキュリティリスクとは?リスクの種類と分析方法、6つの対策を紹介
「脅威」によるリスク
情報セキュリティ上の「脅威」は、企業の情報資産に損失を与え得る要因のことです。主に次の3種類に分類されます。
意図的脅威:
何らかの悪意や目的を持って情報システムに損害を与えようとする行為。
例:不正アクセス、情報の不正利用・改ざん、ウイルス、なりすまし
偶発的脅威:
ヒューマンエラーによって生じる、意図しないリスク。
例:パスワードの漏えい、USBの紛失・盗難
環境的脅威:
自然災害や異常気象など、自然環境から生じるリスク。
例:地震・洪水・落雷による設備の損壊、高温多湿によるシステム障害
「脆弱性」によるリスク
「脆弱性」はシステムや管理体制に内在する弱点や欠陥で、悪用されると大きな被害をもたらす可能性があります。
ソフトウェアの脆弱性:
コンピューターやソフトウェアなどITシステムで発生するセキュリティ上の欠陥。
例:アップデートされていないOS、セキュリティパッチが遅いサービス
文書管理の不備からくる脆弱性:
重要な資料やデータの管理体制が不十分な状態。
例:データに誰でもアクセスできてしまう、アクセス管理が不徹底
立地からくる脆弱性:
データセンターやオフィスが、自然災害などのリスクが高い場所にある状態。
例:地盤が弱い地域、浸水リスクの高い立地、停電や通信インフラが途絶しやすい地域
脆弱性をゼロにすることは非常に困難です。そのため、脆弱性の危険度や発生確率を考慮し、リスクが高いものから優先的に対策を講じることが重要です。
情報セキュリティの10大脅威は?

情報セキュリティリスクは年々変化しており、新たな攻撃手法や脆弱性も登場しています。自社の対策をアップデートするために、定期的な情報収集を心がけましょう。
IPAは毎年情報セキュリティの10大脅威を発表しています。「情報セキュリティ10大脅威 2025」によると、2023年に起きた社会的に影響が大きかったと考えられる脅威は以下の通りです。
| 順位 | 脅威 | 内容 |
| 1 | ランサムウェアによる被害 | PCやサーバーのデータを暗号化し、身代金を要求するマルウェア攻撃。 |
| 2 | サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 | 取引先や協力企業の脆弱性を経由して侵入する手口。 |
| 3 | 内部不正による情報漏えい等の被害 | 従業員や関係者が悪意をもって情報を改ざん・流出させる行為。 |
| 4 | 標的型攻撃による機密情報の窃取 | 特定組織を狙ったフィッシングや脆弱性攻撃などで機密情報を盗む手口。 |
| 5 | 修正プログラムの公開前を狙う攻撃(ゼロデイ攻撃) | ソフトウェアの脆弱性が修正される前に実施されるサイバー攻撃。 |
| 6 | 不注意による情報漏えい等の被害 | メール誤送信や端末紛失など、ヒューマンエラーによる情報漏えい。 |
| 7 | 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 | 公開された脆弱性情報を逆手に取った攻撃。 |
| 8 | ビジネスメール詐欺による金銭被害 | 上司や取引先を装い、振込先を偽装して金銭を騙し取る手口。 |
| 9 | テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 | 在宅勤務などリモート環境の脆弱性を突く。 |
| 10 | 犯罪のビジネス化(アンダーグラウンドサービス) | 犯罪が商業化し、攻撃ツールや手法が取引される。 |
セキュリティ対策では、上記の脅威をすべて視野に入れ、順位が低い脅威でも軽視しないことが大切です。特に攻撃手法や脆弱性は絶えず変化するため、最新情報の収集と対策の更新を継続し、従業員教育や管理体制の強化を進めましょう。
企業が実施するべき情報セキュリティ対策5つ
企業が情報セキュリティを強化するには、システムだけでなく組織全体の意識向上や運用ルールの確立も必要です。以下では、特に重要な5つの対策について詳しく解説します。
- ネットワーク・システムの保護
- 認証・アクセス管理
- 機密データの保護・バックアップ
- インシデント管理
- 従業員に対するセキュリティ教育
1. ネットワーク・システムの保護
企業のネットワークやシステムは、常に外部攻撃のリスクにさらされています。まずは、ネットワークやシステムの保護により、強固なセキュリティ環境を構築することが重要です。具体的には、以下のような対策を講じましょう。
- ウイルス対策ソフトの導入・更新:最新のウイルス定義を保ち、マルウェアやウイルスからシステムを守る
- ファイアウォールの設置:不正アクセスや外部からの攻撃をブロックする
- 定期的なソフトウェアのアップデート:ソフトウェアの脆弱性を修正する
- 脆弱性スキャンとペネトレーションテストの実施:システムの脆弱性を診断して攻撃のリスクを軽減する
これらの対策を通じて、外部からの攻撃やシステム障害を未然に防ぎ、安定的に業務を継続できる環境を整えられます。
2. 認証・アクセス管理
認証とアクセス管理を適切に行うことで、内部不正や不正アクセスのリスクを低減できます。パスワードを強化し、誰がどの情報にアクセスできるのかを明確に制御することが基本的な対策となります。具体的には、以下のような対策が効果的です。
- パスワードポリシーの徹底:複雑なパスワード設定、定期的な変更を義務付ける。
- アクセス権限の最小化:業務に必要な範囲だけを付与し、過度に権限を与えないようにする。
- 多要素認証の導入:ワンタイムパスワードや生体認証など、複数の方法を組み合わせる。
- ログの取得とモニタリング:アクセス履歴を追跡し、不正の兆候を早期に把握する。
これらの対策を実施することで、組織内の情報流出リスクを抑えつつ、万が一の不正行為があっても早期に追跡が可能となります。アクセス権の整理など準備には時間がかかりますが、重大な被害を防ぎ、企業の信用を守る効果が期待できるでしょう。
3. 機密データの保護・バックアップ
企業が扱う情報の中でも、個人情報や営業上の機密データは特に慎重に管理する必要があります。これらのデータが流出・消失すると、企業の信用失墜や法的責任につながるため、データの暗号化とバックアップによるデータ保護が不可欠です。
- 暗号化(保存・通信時):データ流出時に、第三者に内容を読み取られにくくする。
- 定期的なバックアップ:データの喪失を防ぎ、システム障害時に迅速な復旧を可能にする。
これらの対策を実施することで、万が一のトラブル時にも重要なデータを速やかに復旧でき、業務の継続性を確保できます。データ保護の強化は、顧客や取引先の信頼を維持し、企業の競争力を高めるためにも不可欠です。
4. インシデント管理
インシデント管理とは、正常に利用できないシステムを復旧に導くための一連のプロセスです。具体的には、以下のような取り組みを含みます。
- 異常発見・報告:監視やアラートで兆候を捉え、即時に記録
- 連絡・エスカレーション:担当者へ共有し、迅速対応
- 原因特定・対処:不具合や攻撃経路を把握し、復旧策実施
- 復旧・事後検証:正常化後に再発防止策を検討・改善
適切なインシデント管理を実施することで、万が一のトラブル時もシステムを迅速に復旧し、事業への影響を最小限に抑えられます。
以下のページでインシデント管理について詳しく解説しているので、より詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
関連記事:インシデント管理とは?ITシステムにおける具体的な手順、効果的に運用する方法を解説
5. 従業員に対するセキュリティ教育
システムやツールの導入だけでは、十分な情報セキュリティ対策とはいえません。従業員一人ひとりが適切なセキュリティ意識を持つことが、企業全体のリスク低減につながります。先に触れた「情報セキュリティ10大脅威 2025」でも、不注意による情報漏えい等の被害は6位に入っています。
ソーシャルエンジニアリングやフィッシング詐欺などの手口は巧妙化しており、被害を防ぐには定期的な研修や勉強会の実施が欠かせません。また、社内のセキュリティポリシーを明確にし、全員が理解・遵守できる環境を整えることも重要です。
従業員に対する継続的な教育を実施することで、人為的ミスを減らし、悪意ある攻撃にも対応できるリテラシーを社内全体に浸透させることが可能になります。これにより、企業の情報セキュリティレベルを向上させ、リスクを最小限に抑えることができます。
効果的な情報セキュリティ対策の4つのポイント
以下では、効果的な情報セキュリティ対策を実施するためのポイントを解説します。
- 複数の対策を組み合わせる
- 最新の脅威について情報収集する
- リスク評価に基づいて改善する
- 自社にノウハウがない場合は専門家に相談する
複数の対策を組み合わせる
単一の防御策だけに頼っていては、どうしても抜け穴が生まれてしまいます。セキュリティ攻撃は多角的に行われるため、ファイアウォールやウイルス対策ソフトといった単独の手段だけでは充分とはいえません。そのため、複数のセキュリティ対策を組み合わせることが大切です。
- ウイルス対策ソフト:マルウェアやランサムウェアの侵入を検知・防御
- 端末制御ソフト:端末の状況を監視・制御し、漏れのない管理を実現
- エンドポイントセキュリティ:端末ごとのセキュリティ対策を強化し、内部からの攻撃を防ぐ
- バックアップ&復旧:データを定期的にバックアップし、万が一のシステム障害に備える
これらの対策を組み合わせることで、外部からのサイバー攻撃や内部の脆弱性をカバーし、さまざまな脅威に対抗できる環境を構築できます。
最新の脅威について情報収集する
日々新たな攻撃手法が登場するなかで、企業のITリテラシーや人材不足を理由にセキュリティ対策を後回しにすると、思わぬところで脆弱性を突かれる恐れがあります。専門メディアやセキュリティベンダーのニュースレターを定期的にチェックし、新種のマルウェアやフィッシング詐欺などの流行状況を把握しておくことが重要です。
新たな脆弱性が発覚した場合は素早くパッチを適用したり、社内のセキュリティポリシーを見直すようにしましょう。継続的な情報収集と迅速な対策のアップデートを繰り返すことで、常に最新の脅威に備えた体制を維持できます。
リスク評価に基づいて改善する
情報セキュリティ対策を効果的に進めるには、リスク評価を実施することが不可欠です。適切なリスク評価を行わないと、深刻な脆弱性が見逃され、攻撃を受けるリスクが高まります。
新たなセキュリティ対策を導入する際は、まずリスク評価を行い、影響が大きい脆弱性から優先的に対策を進めることが重要です。これにより、限られたリソースを有効活用し、より効率的な対策を講じることができます。
自社にノウハウがない場合は専門家に相談する
情報セキュリティ対策を適切に実施するには、専門的な知識や経験が必要です。しかし、多くの企業では十分なITリテラシーやセキュリティノウハウがなく、十分な対策を講じられていません。そのような状態では、重大なインシデントにつながる可能性があります。
こうしたリスクを回避するためにおすすめなのが、専門家からの支援を受けることです。外部の専門家に相談することで、自社のセキュリティ課題を明確にし、限られたリソースの中で効果的な対策を講じることができます。
自社での対策が難しいと感じた場合は、早めに専門家に相談し、リスクを最小限に抑える体制を整えましょう。
企業が抱える情報セキュリティの課題
ここでは多くの企業が抱えている、情報セキュリティの課題を解説します。
- スキル・ノウハウ不足
- 人手不足
- 経費上の問題
これらの課題を放置すると、サイバー攻撃の被害や情報漏えい、業務の停止といった重大なリスクにつながる可能性があります。ここでは、企業が直面する代表的な3つの課題について解説します。
スキル・ノウハウ不足
多くの企業にとって、情報セキュリティ対策を進める上での大きな課題が、スキルやノウハウの不足です。IPAの調査によると、IT人材の「質」や「量」が不足していると感じる企業は7割を超えています。
スキルやノウハウが不足していると、十分なセキュリティ対策を実施できない可能性があります。こうした課題を解決するためには、社内での研修や情報セキュリティ教育の強化が重要です。
また、自社での対応が難しい場合は、専門家のアドバイスを受けることも有効な選択肢となります。
参考:デジタル時代のスキル変革等に関する調査(2023年度)
人手不足
多くの企業で情シスの人手不足が深刻化しています。専任担当が少ない「ひとり情シス」状態では、脆弱性管理やインシデント対応といったセキュリティ対策が後回しになり、セキュリティ事故につながる恐れがあります。
対策としては、外部リソースの活用がおすすめです。アウトソーシングサービスなどを活用することで、担当者の負担を軽減できます。また、クラウドサービスや自動化ツールを導入することで、業務効率化を図ることも有効です。
限られたリソースで適切なセキュリティ対策を実施し、企業の安全性を確保しましょう。
経費上の問題
情報セキュリティ対策には一定のコストがかかるため、十分な予算を確保できない企業では、対策が後回しになりがちです。しかし、コストを理由に脆弱性を放置すると、情報漏えいやサイバー攻撃のリスクが高まり、結果的に大きな損害につながる可能性があります。
予算に制約がある場合でも、セキュリティ対策を怠ることはできません。そのため、コストを抑えつつ、リスクに応じた適切な対策を講じることが重要です。
例えば、アウトソーシングを活用して専門家の支援を受けることで、限られたリソースでも効果的な対策を講じることができます。また、クラウド型セキュリティサービスや自動化ツールを活用すれば、コストを抑えつつ、運用負担を軽減できます。
情報セキュリティ対策は企業の信頼を守るための重要な施策です。優先度の高い対策から実施し、段階的に強化することで、効果的なセキュリティ体制を構築できます。
情報セキュリティ対策なら「IT顧問 情シス君」にお任せ!
本記事では、情報セキュリティ対策の概要や3大要素、具体的な対策方法などを解説しました。自社の大切な情報資産を守るには、最新の脅威や脆弱性を踏まえてセキュリティ対策を講じる必要があります。
しかし、「どこから手をつければいいのかわからない」「自社にノウハウがなく、適切な対策を講じられない」と悩んでいる企業も少なくありません。
そのような課題を抱えている方は、ぜひ「IT顧問 情シス君」にご相談ください。情シス君は、中小企業の情報システム業務を支援するサービスです。情シス君を利用することで、セキュリティ対策で以下のようなメリットが得られます。
人手不足の解消
- セキュリティ専門スタッフが不足している企業向けに、スポット支援やアウトソーシングを提供
- 24時間対応のヘルプデスクで、迅速なサポートが可能
ノウハウ不足の補完
- セキュリティポリシーの策定やリスク評価の支援
- フィッシング対策、アクセス管理強化など、最新のセキュリティ対策をサポート
予算に応じたセキュリティ強化
- 必要な業務だけを依頼できる従量課金制でコスト最適化
- 予算に合わせた最適なセキュリティ対策を提案
セキュリティ対策以外にも、情報システムに関するあらゆる課題に対応可能です。小さな悩みでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。